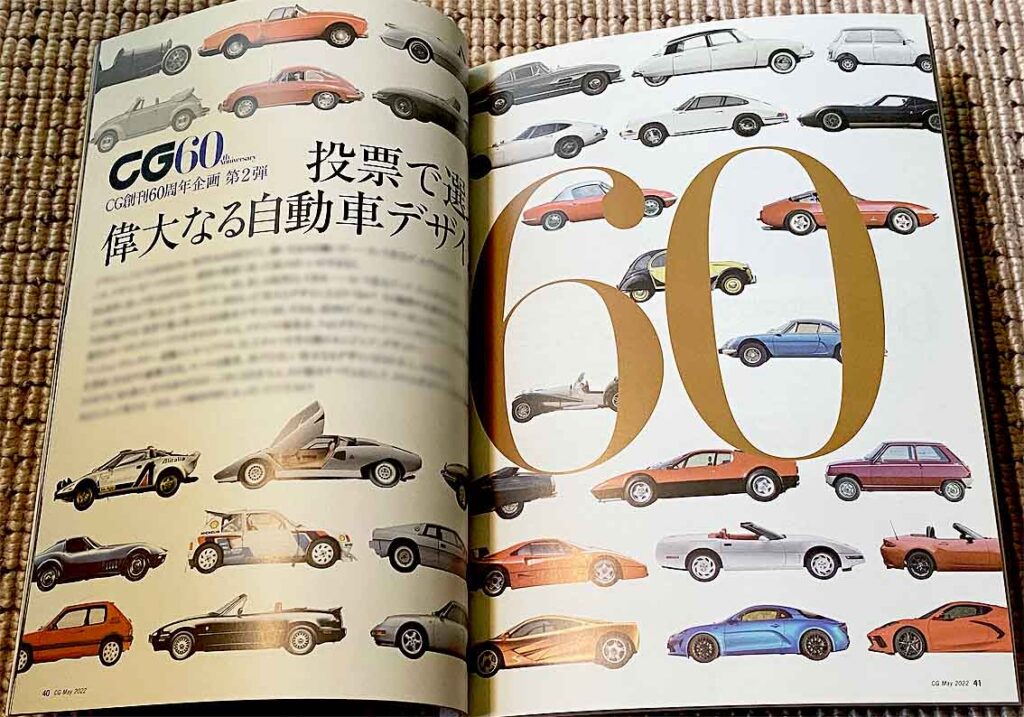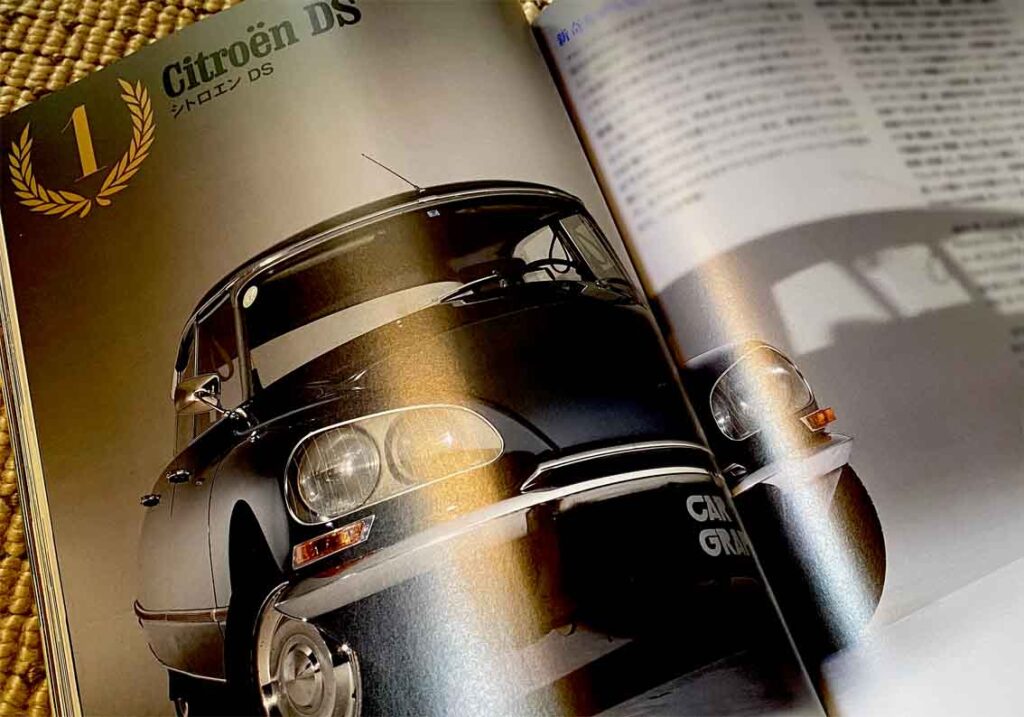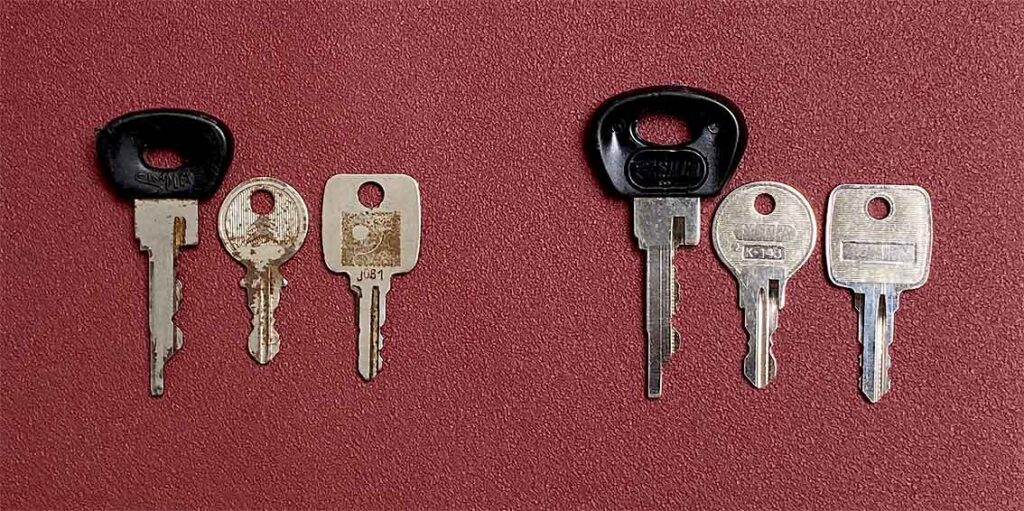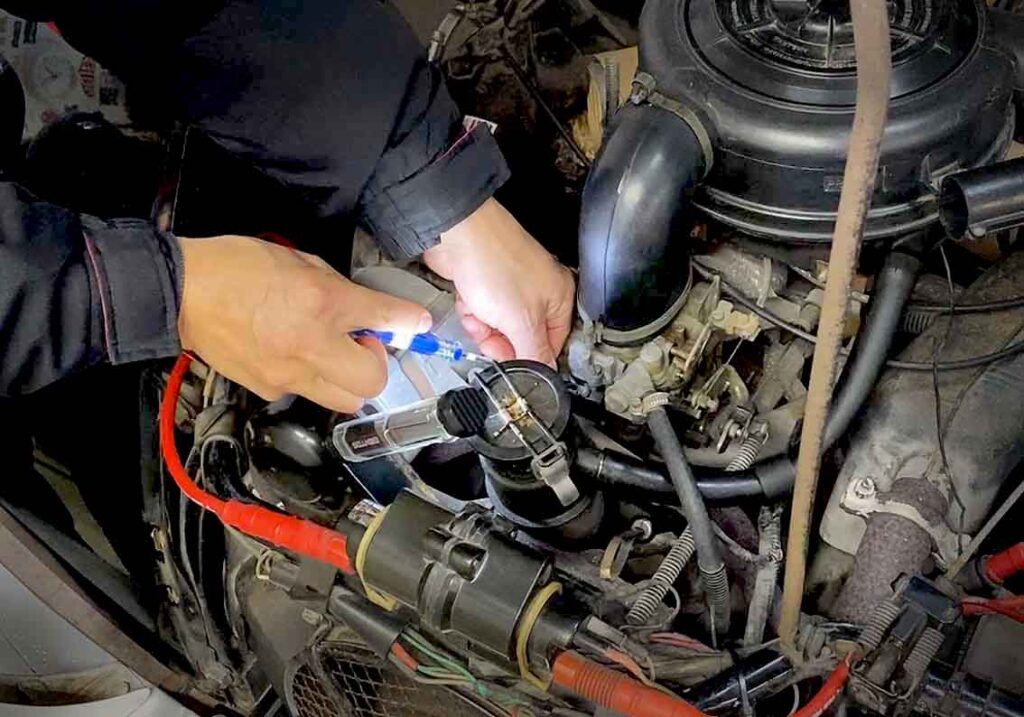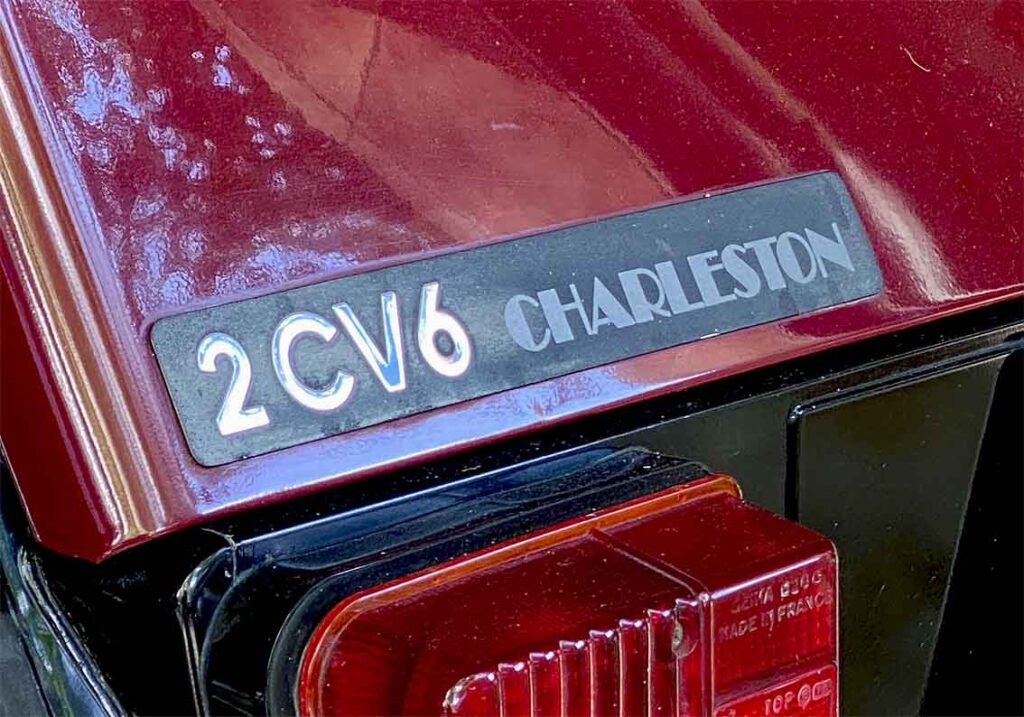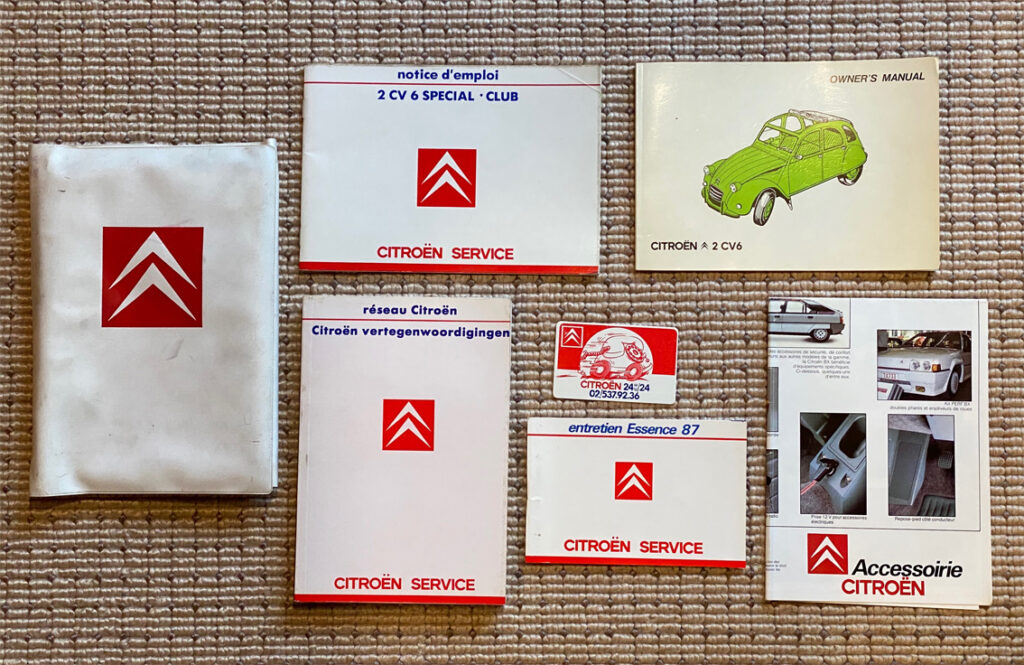タイヤを何にするか、これは車好きにとっては悩ましくも楽しいものです。
とくにアジアンタイヤは、低価格と性能をいかに見立てるか、独特な冒険的なワクワク感が伴います。
ゴルフではMOMOやナンカンも使いましたが、最後に履いていたハンコックのオールシーズンはとくに上質感もあり、韓国製タイヤは近年欧州車の新車装着タイヤとしても認められているというのも頷けるものがあります。
で、韓国製タイヤにするつもりだったのですが、この面での草分け的存在でもあるSさんによると、COOPER(アメリカのブランド、中国製)がちょうどセールになっているとのこと。
COOPERは、SさんのBMW325iに着けられたのがかなり上質な印象だったから、ならばとこれに決めました。

さっそく交換店の予約、当日はリアシートを倒し、使いふるしのシーツを広げ、届いたタイヤを積み込んでいざ交換へ。
作業は30分少々、ついにヒビ割れタイヤとおさらばして走り出したら、意外に硬目の印象で「ん!?」となり、、、帰宅してすぐ空気圧を計ったところ、概ね2.6〜7ぐらい。
C3の指定空気圧は2.3barで、冬場は走れば0.1ぐらい上がるからまずは2.4にして、あとは段階的に下げては試走を繰り返し、ついに2.0barにしたら、いくらか当たりが穏やかにはなったけれど、基本の骨太さみたいなものが残ります。


このCOOPER ZEON RS3-G1というのはスポーツ指向のようで、届いたときサイドウォールの硬さが少し気にかかっていたのが、やはりそのような乗り心地でした。
とはいえ、しっとりして回転もとてもきれいだから、これはハイドロ向きのタイヤではないか?と思ったり、、、
皆さんには釈迦に説法ですが、ハイドロはよりソフトな乗り心地を目指して柔らかいタイヤをつけると、はじめは好印象に思えても、だんだん期待にそぐわない結果となることはないでしょうか?
ハイドロが柔らかいタイヤの介入をあまり好まないのか、あのオイルとガスのもたらす官能的なフィールを引き出すには、むしろ腰のあるしっかりしたタイヤであるほうが適切なのではないか?と思ったことは一度や二度ではありません。
空気圧にしても同様、低めにすると逆にドスンバタンというフィールになるように感じるのですが、、どうでしょう?
…これは本題からも逸れるのでこれぐらいにしておきます。
C3の日本仕様のタイヤサイズは205/55R16、限定車等には205/50R17というのさえあり、これは初代C4カクタスも同様、ちなみに先ごろ発表された新型C3も205/50R17とのこと。
205/55R16は一回り大きいゴルフがまったく同じであったし、SさんのBMW325iでも指定サイズとのことで調べてみると、アルファロメオ166とかランチア・カッパとか、メルセデスEクラスとか、クラウンアスリートといった大型車の名がいくつも出てきて、これだけでもC3のようなBセグメントカーには過剰サイズではないか?という疑念は拭えません。
実はducaさんから早い時期にこの点を指摘され、すこし細いタイヤにしませんか?とやんわり提案されたのですが、私はけっこうオリジナル主義であるため耳をかさなかったことも、のちに悔やまれることになります。
過剰サイズではないか?と思われる症状としては、乗り心地がドタドタして車体が不必要に揺すられるし、なにより耐え難いのは路面状況によってチョロチョロとハンドルを取られることでした。
他の何を我慢しようとも、いやしくも前後にダブルシェブロンを戴いた車が、直進性に難があるのは容認できません。
それからというもの、空気圧と乗り心地/操縦性(安定性)の最良の妥協点を探るべく、来る日も来る日も空気圧を足したり抜いたりする日々を送りましたが、多少の変化はあるものの根本的な解決とはならず、輾転反側を重ねた末、ついには細いタイヤに履き替えるしかないという結論に達してこれを敢行することになりました、、あーあ。
アジアンタイヤがお安いことは、こういうとき経済的損失が最小限で済むことはせめて救われるところで、これがミシュランやBSなどを奮発していたなら、さすがそうも行かないでしょうね。