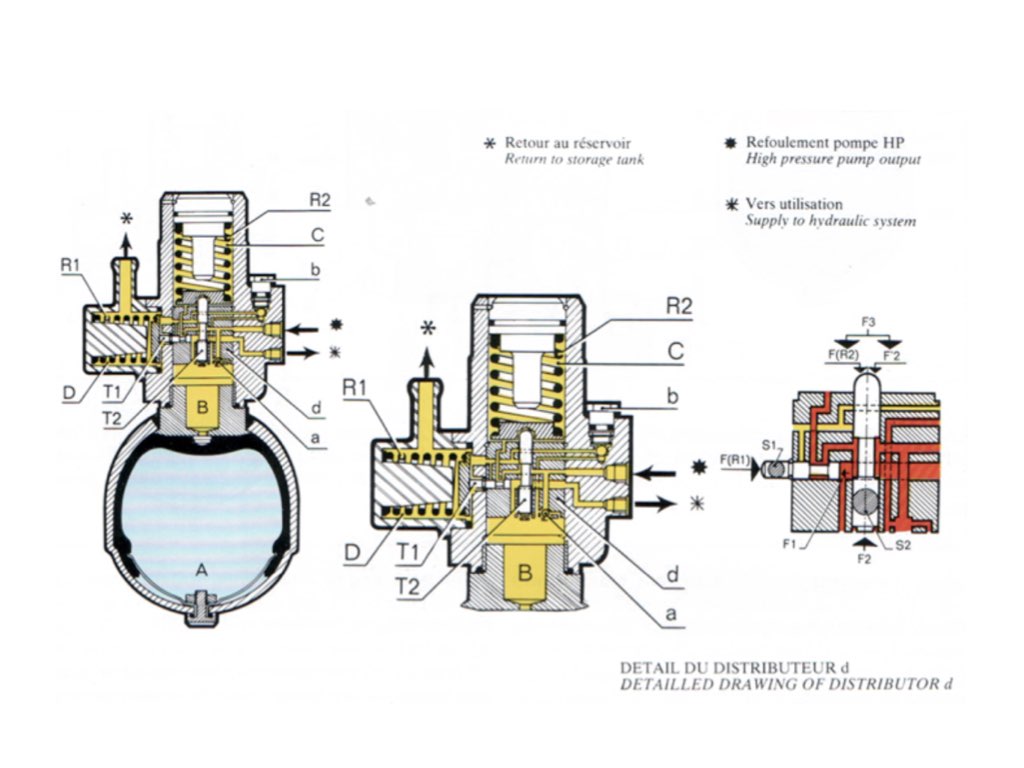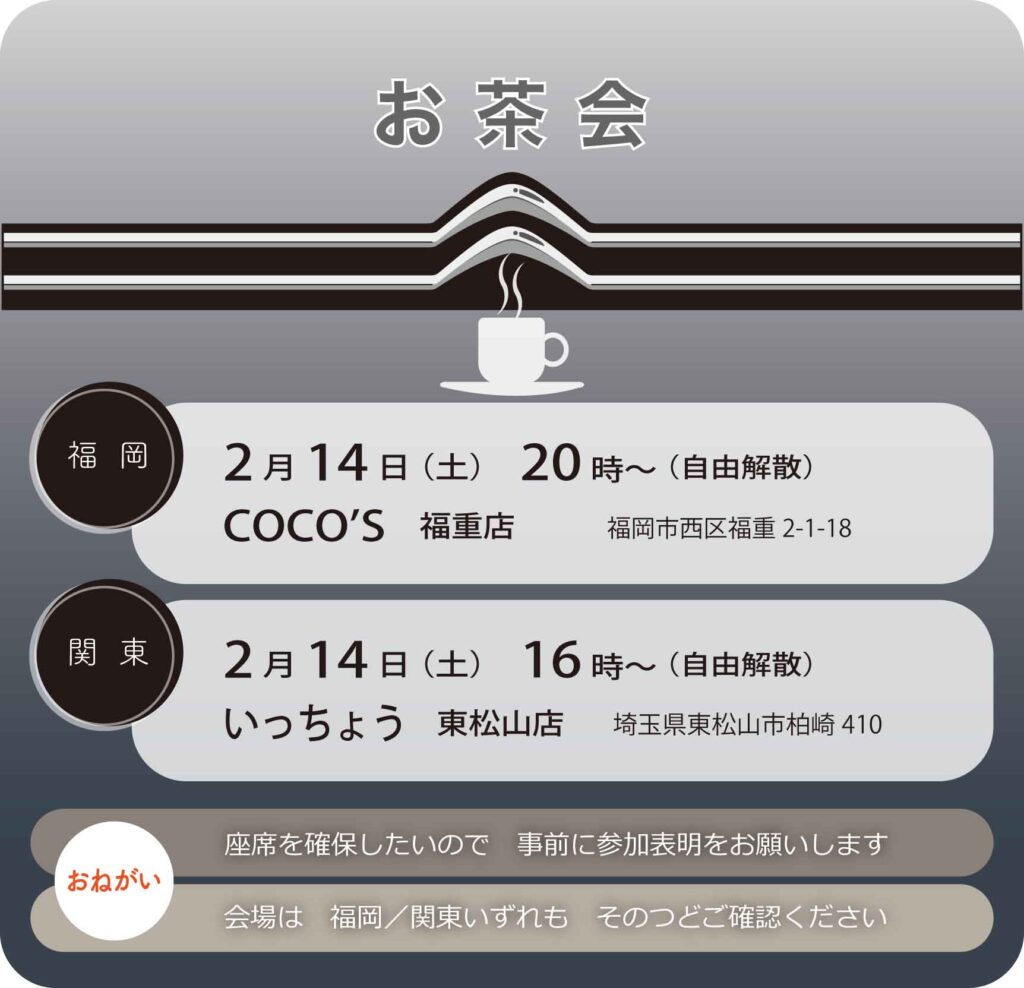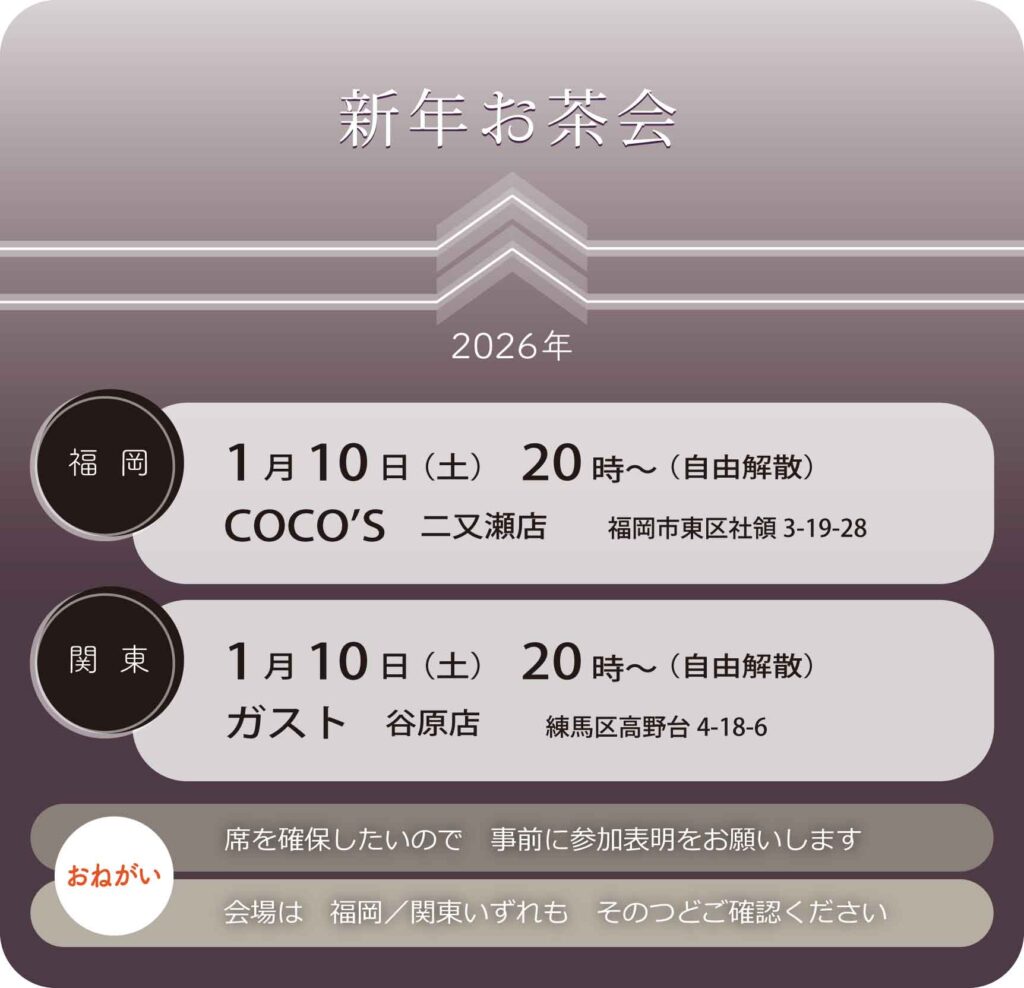タイヤの話題が続いたので、それ以外の話を。
▶CarPlay
このC3には「純正ナビ」が付いていましたが、簡単に云ってしまうと平凡な日本製ナビが、ダッシュボードのモニターに映し出されるというだけのもの。
ここ数年で事情は一変したようですが、以前は輸入車に「純正」と称する日本製ナビを組み込むか、各自市販品を買って取り付けるか、あるいはナビゲーション無しに甘んじるかのいずれかでしたね。
C6のような高級車では標準装備とするため、ダッシュ上部にカロッツェリアナビを押し込み、連動してエアコンのセンター吹き出し口の半分以上を潰すまでして日本製ナビを組み込むなど、C3の「純正ナビ」もそんな時代の最終期であったらしいことが窺えます。
ただしダッシュボード下部にはUSBの差込口があり、すでに海外では新時代が到来していることも静かに語っています。
巨匠のご子息によれば、ずいぶん試されたらしいけれども、スマホとの連結は「できない」とのこと、しかしAppleのサイトではC3は初期モデルからCarPlayが使用できると記されているし、ネットには使えている動画もあるから、あきらめきれずBluetoothで繋ぐワイヤレスアダプターを購入したものの、やはり頑として繋がらない。
ついにディーラーに問い合わせると「コンピューターの設定変更で使用できるようになる」との回答。
ではすぐに行ってみたいところ、それができないのが今どきで、いかなることでも「事前予約が必要」で最短の予約をとってからディーラーを訪れました。
作業は30〜40分ほどで終了、帰り道ワイヤレスアダプターを差し込むと、とくに設定もせずあっさりCarPlayは繋がり、このときから純正ナビは二軍降下と相なりました。

ひとつ困りごとは、CarPlay使用中電話がかかってくると、呼出音から会話の内容まで盛大に車内のスピーカーから筒抜けとなるし、LINEなどは発信者の名前までモニターに表示されるから、それは必ずしもありがたくはないのですが、設定でどうにでもなることを例によって「私が知らないだけ」かもしれません。
▶▶アイドリング・ストップ・キャンセラー(ISC)
ご多分にもれずアイドリング・ストップ機能が装着されていますが、個人的なドライバー視点で言わせてもらうと、これほど煩わしく迷惑なものはありません。
物理スイッチがあればまだしも、C3はタッチパネル上で[車両設定画面]を呼び出し[OFFにする]という手順を踏まなくてはならず、しかも一度エンジンを切ると必ずONに戻るから、始動するたびにこの操作が必要となり、乗ってパッと走り出すということができません。
これを怠ると、アイドリング・ストップの介入はのべつまくなしで、信号停車はもちろん、一旦停止や右折など時を選ばずやたらエンジン停止/再始動を繰り返します。
kunnyさんは早々にC3エアクロスにISCを取り付けられてこの苦境から脱出された由、同じものを!となりましたが、すでにネット上では見当たらなくなっており、直接発売元に掛けあってくださいました。表向きの販売は終わっている由で、メール往復は年をまたぎ1月上旬ついに入手へと至りました。
さらにはkunnyさんからは、取り付けも「僕がやってあげますよ」とのありがたいお申し出があり、いうまでもなく私は自分じゃできないからお願いすることに。
作業はメーターユニットを引き出して、その奥の配線の一部にISCを組み込むだけだからかんたん!と仰せですが、私にしてみたら自分でメーターを外すこと自体、考えも及ばないことです。
パーツ・キットの中には、メーターを外す際に使うらしいプラスチック製の「こじ開け用ヘラ」のようなものが入っており、執刀医であるkunnyさんはそれをパネルの合わせ目などにグイと差し込み、ぎゅうぎゅう力を込めてこじったり、ひっぱったり、ときに二の腕がプルプル震えるほど相当ハードな作業だったのは驚きでした。

ときおり「バキ」とか「ボキ」とかの恐ろしげな音もするから、横で心臓バクバクでしたが、kunnyさんはそんなことは意に介す様子もなく作業を継続され、無事取り付けは終了、動作確認でもアイドリング・ストップは「しなく」なり、さらにタッチパネル操作によって「する」状態に戻すこともできるという、なかなかのすぐれものでした。
自分で作業や修理をされる方のことを「武闘派」などというけれど、これぞまさしく武闘的でありました。
その荒療治の甲斐あって、エンジンをかけたらすぐに走り出せるようになり、離陸前のパイロットのようなことをしなくて済むようになったのは大いに助かっています。

↑これら2件は、いずれも車いじりの味わいとか情緒の伴わない、パソコンいじりのようなものですが、現代の車はなにかしらこういうものが避けられない時代になりました。
▶▶▶あえてハロゲン維持
左右上部にLEDのデイタイムライトが白く光っているのに、ヘッドライトは旧式なハロゲンだから黄ばんだ光色がことさら目立って、たまたまHIDの換装キットをもっていたので、ducaさんに交換作業をお願いして快諾していただいていたのですが、しだいにこれはこれで温かな味わいかもしれない、、というような気がしはじめました。

ヘッドライトを今どきのクールな白にしたら、C3のおだやかなフロントの表情が損なわれ(といったら言いすぎかもしれないけれど)、このほうがランタンのような風情があるようにも思えてきたこともあり、当分このままにしておくことに。
ヘッドライトは白いほど良いというのも現代人の思い込みかもしれず、LPレコードやフィルムカメラが見直されているように、ハロゲンも悪くないと思えるようになりました。
もちろん車種にもよりけりですけどね。